食のインフラを支える食品商社が挑む脱炭素経営。使用電力を実質100%再エネ化 *へ
三菱食品株式会社

経営企画本部 サステナビリティグループ カーボンニュートラル推進ユニット ユニットリーダー 矢野様
グループマネージャー 岩野様
カーボンニュートラル推進ユニット 主任 安川様
カーボンニュートラル推進ユニット 渡部様
カーボンニュートラル推進ユニット 主任 岡野様
課題
- 全国約400拠点の物流センターで使うエネルギーの約9割が電力由来
- 自社契約電力拠点は再エネ化を完了していても、約4割の賃借拠点の再エネ化が困難
- 2030年目標達成に向けた、実効的な削減策の検討が急務
ソリューション
- コストと品質を重視した非化石証書調達
インパクト
- 物流拠点の電力を実質再エネ化しCO2排出量を大幅削減
- 省エネ・創エネ・再エネの三本柱で持続的削減体制を構築
- 早期導入により再エネ創出へ貢献、社会全体の脱炭素を促進
日本の食を支える食品商社が挑む、全国400拠点のCO2排出量削減

三菱食品は、国内外の加工食品、低温食品、酒類および菓子の卸売を主な事業内容とし、さらに物流事業やその他サービス事業も展開する食品商社です。食品卸売業という中間流通を担う立場として、平時はもちろん災害時にも全国各地への食品供給を通じて生活者の安全・安心を守り、流通の人手不足や食品廃棄量の削減といった社会課題にも、サプライチェーン全体の調整機能を発揮して応えています。
2011年に複数の会社が統合して誕生した当社は、「フルカテゴリー」を扱う体制を強みに、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、ドラッグストア、ECサイト、外食産業など多様なお客さまに商品をお届けしています。常温から冷蔵・冷凍まであらゆる温度帯の商品を一貫して取り扱う物流体制は、まさに食のライフラインを支える中核となっています。
当社でサステナビリティ推進の機運が高まったのは2021年ごろです。食品流通業界は非財務情報の開示が遅れていましたが、上場企業としてこのままでは置いていかれるのではないかという危機感から、2022年にサステナビリティグループを新設。社長自らが旗振り役となり、全社的な取り組みを始めました。これを機に、非財務情報の積極開示にも舵を切り、パーパスを「食のビジネスを通じて持続可能な社会の実現に貢献する」と定義。さらに2024年5月には「サステナビリティ重点課題の同時解決」を新たに加えました。とはいえ、当初は社内で「サステナビリティって何?」という声も多く、啓発からのスタート。地道な社内説明や経営層との対話を重ね、意識の土台を築いてきました。
次の課題は、CO2排出量の削減でした。全国約400拠点の物流センターで使うエネルギーの約9割が電力です。省エネ機器の導入推進に加え、2022年度には自社の契約電力をすべてCO2フリープランに切り替えましたが、賃借拠点が全体の4割を占めており、自社では契約変更ができないという壁がありました。これらの電力消費量を削減しなければ2030年目標の達成は難しいと考え、非化石証書の活用を検討しました。
クレジットに関する専門性と誠実な伴走支援で、信頼して進められると確信
Carbon EXを知ったのは、2023年度に参加したアスエネ社のウェビナーがきっかけでした。非化石証書の仕組みや市場動向を非常に丁寧に解説しており、「ここなら信頼できる」と強く感じました。
当初は「非化石証書で本当に大丈夫か」という不安もありました。電力会社のCO2フリープランのように分かりやすい商品ではないため、社内でも慎重な声が上がっていたからです。Carbon EXは、証書の仕組みや信頼性を根拠データとともに丁寧に説明くださり、社内説明の際にはその資料を活用させていただきました。結果として、「コストを抑えながら再エネ化が進むなら導入しよう」という共通理解が社内に生まれました。加えて、手数料体系の透明性と非約定時は手数料不要という価格の優位性も選定のポイントとなり、Carbon EXを起用するに至りました。
他社とは価格以外の面でも比較を行いましたが、Carbon EXは研究の深さと熱量が明らかに異なりました。担当者の知見も非常に豊富で、実際に非化石証書の購入に踏み切る局面でもCarbon EXが“先生”のように伴走支援してくださり、いまでは全幅の信頼を寄せるパートナーです。
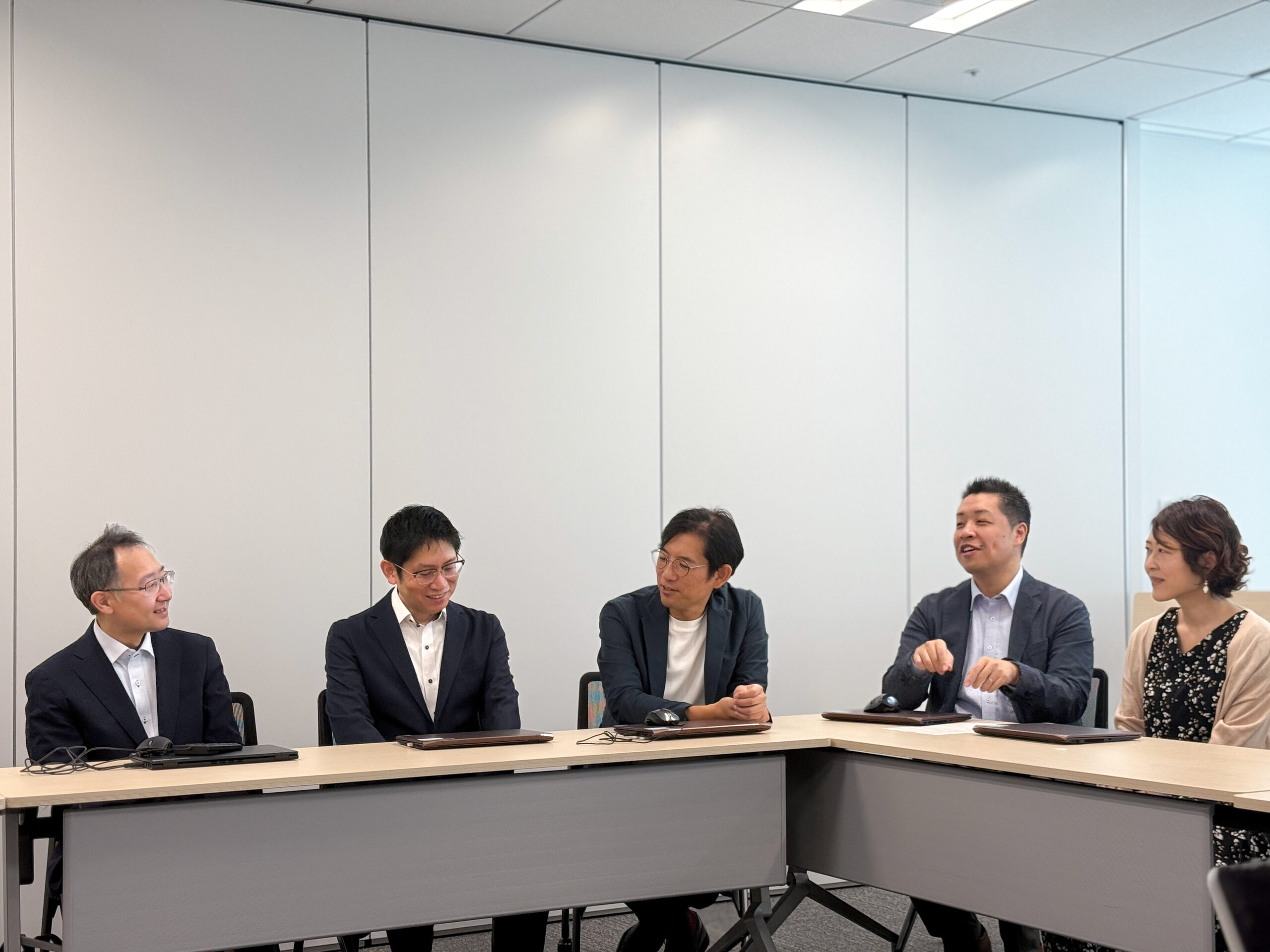
“実質再エネ化”だけでは終わらせない。省エネ・創エネとの三本柱を目指す

非化石証書を活用したことで、物流拠点の電力は実質的に再エネ化され、CO2排出量を大幅に削減できました。ただ、私たちはそこで満足するつもりはありません。
非化石証書も脱炭素の有効な手段の一つと考えますが、本質的にはエネルギー使用量を減らす省エネと、自ら再エネを生み出す創エネの両輪で、持続的な削減を目指すことが重要です。すでに2拠点で大規模な太陽光パネルを導入しており、今後も新拠点や耐荷重条件を満たす施設には、オンサイト発電を積極的に導入していきます。
またScope1の削減にも取り組んでいます。Scope1は物流子会社のトラック輸送に伴う軽油や物流センターでのドライアイス使用など、食品流通の維持に不可欠な要素が多く、容易ではありません。その削減に取り組むほか、秋田県由利本荘市との連携によるカーボンクレジット創出やその活用を通じ、Scope1の削減を目指します。
当社は2025年に創立100周年を迎えました。節目の年に上場を終え、次の100年に向けて新たなフェーズへ。2024年度、パーパスに「サステナビリティ課題の同時解決」を加え、社員の意識も大きく変わりつつあります。社内では「SDGs Awards」を設け、地域農家との協業による食品廃棄削減など、現場発の取り組みを表彰。応募件数は年々増え、従業員のモチベーションも高まっています。
非化石証書を早期に導入することは、単なる削減施策ではなく再エネ創出への投資です。早期から積極的に取り組むことで社会全体の変革につながり、未来への責任を果たせるはずです。
私たちは、次の100年も「なくてはならない存在」であり続けたい。食を通じて社会をより良くしていくことが当社の変わらぬ使命です。Carbon EXとの協働を通じて、脱炭素の波をサプライチェーン全体に広げ、次世代に持続可能な食のインフラを残していきます。
* 実質再エネ100%:前年度実績を基礎に、今年度の再エネ利用率100%相当の達成を目指しています。ただし、酷暑などの外部要因により電力使用量が増加した場合、実績値が計画から乖離する可能性があります
企業プロフィール

三菱食品株式会社
業種:食品卸売業
社員数:3,298名(2025年4月1日現在)
所在地:東京都文京区小石川一丁目1番1号
三菱食品は、国内外の加工食品、低温食品、酒類及び菓子の卸売業を主な事業内容とし、さらに物流事業及びその他サービス等の事業活動を展開しています。パーパスに「食のビジネスを通じて持続可能な社会の実現に貢献する」を掲げ、サステナビリティ重点課題の同時解決に取り組んでいます。
※掲載内容は取材当時のものです。